【特集第15弾:栃木のお米】特徴やおすすめのお米をご紹介!

熊本県の北部を流れる「菊池川」流域では、2,000年前から米作りが行われており、江戸時代には「天下第一の米」と呼ばれる肥後米の中心産地として発展しました。現在も豊かな自然と水を生かして、おいしいお米が作られており、生産量は全国16位と、西日本有数の米どころです。
本記事では、そんな熊本県で主に栽培されているお米の品種、熊本県が開発したお米の特徴について詳しくご紹介します。

かつて肥後国と呼ばれていた熊本県は、九州の中央部の西側に位置しており、福岡県・大分県・宮崎県・鹿児島県に囲まれています。北には福岡との県境にある筑肥山地、南には国見山地が広がっています。また、西側の八代海の沖には天草諸島、東には世界最大級のカルデラを有する阿蘇があり、自然がとても豊かな県です。
面積は約7,409㎢で全国15位、阿蘇山や九州山地に源を発する菊池川、白川、緑川、球磨川などの河川が流れています。これらの河川は、菊池平野や熊本平野、八代平野を潤し、水資源にも恵まれています。また、三方を山に囲まれているため、天草地方を除き、夏は暑く冬は寒い内陸性の気候です。
熊本県では、熊本平野や八代平野の平坦地から、阿蘇地域などの高冷地、天草・芦北の海岸しょなど、さまざま地形や気候を生かして、多くの農作物が栽培されています。主な農産物として、野菜や花き、果樹などの園芸作物があり、ほかにも米、い草、葉たばこ、茶などの多彩な農産物を栽培しています。
令和4年の農業産出額は、約3,512億円で全国第5位に輝きました。特にトマト、すいか、メロン、かんきつ類、葉たばこ、い草、宿根カスミソウは、全国でもトップレベルの生産量を誇っています。
参考: 熊本県新規就農支援センター「くまもとの農業概要2024」
熊本県では、温暖な気候を生かして、米づくりが盛んに行われています。令和5年度のデータによると、お米の作付け面積は3万ヘクタール、収穫量は15万5,400トンで、そのほとんどが主食用です。西日本では、兵庫県や福岡県に次いで3番目にお米が多く栽培されています。
近年、全国的に新しい品種が登場し、産地間の競争が激しくなっています。一方、熊本県では「良食味ブランド米づくり」「高付加価値米づくり」「多収性品種の普及」といった地域特性を生かし、特色ある米づくりに取り組んでいます。
参考:農林水産省「令和5年産作物統計(普通作物・飼料作物・工芸農作物)」

熊本県で作付けされているお米の品種は、1位ヒノヒカリ(46.4%)、2位森のくまさん(13.3%)、3位コシヒカリ(11.5%)となっています(令和5年度産)。この章では、それぞれの品種の特徴について紹介します。
「ヒノヒカリ」は、宮崎県総合農業試験場が、コシヒカリ(越南17号)と黄金晴(愛知40号)を交配して育成した品種です。平成元年(1989)年に命名登録され、その年に熊本県でも奨励品種に採用されました。「ヒノヒカリ」の名前は、西日本や九州地方を意味する「日(太陽)」と、お米が光り輝く様子から名づけられました。西日本を中心に広く作付けされており、品種別の作付面積の割合はコシヒカリ、ひとめぼれに次いで3位です。
他の品種と比べるとやや小粒ですが、厚みがある食感と食味が人気のお米です。あっさりとした味のため、さまざまな料理に合わせやすいという特徴があります。また、冷めてもおいしいので、お弁当やおにぎりにも向いています。
参考:米穀安定供給確保支援機構「日本で多く栽培されているお米の品種を教えてください」
関連記事:ごはん彩々「ヒノヒカリ誕生秘話 耐性や栽培特性より、「コシヒカリ」と同等という食味へのこだわりが、西の横綱「ヒノヒカリ」を育てた!」
「森のくまさん」は熊本県が育成した初めてのオリジナルの品種です。熊本県農業研究センターにおいて、「コシヒカリ」と「ヒノヒカリ」を交配させて育成し、平成9(1997)年に誕生、平成12(2000)年に品種登録されました。「森のくまさん」という名前は、一般公募により命名され、森の都「熊本」で生産されたお米という意味が込められています。
「コシヒカリ」と「ヒノヒカリ」の食味を受け継いでおり、うま味ともちもち食感があり、日本穀物検定協会が実施している「令和5年度産 お米の食味ランキング試験」では、県北の「森のくまさん」が特Aの評価を獲得しています。
「コシヒカリ」は、昭和31(1956)年に誕生した品種ですが、現在も全国の品種別作付け面積においてトップを守り続けており、「お米の王様」と呼ばれています。熊本県でも昭和56(1981)年から奨励品種に採用されていて、現在も品種別の作付けは第3位(11.5%)です。粘りが強く、食味がとても良いことから、熊本県産の「コシヒカリ」には県内外にたくさんのファンがいます。
参考:熊本県「令和5年度(2023年度)主要農作物奨励品種特性表」
参考:米穀安定供給確保支援機構「令和5年産 水稲の品種別作付動向について」
「森のくまさん」の他にも、熊本県農業研究センターが育成した熊本オリジナルの品種があります。
「くまさんの力」は、熊本県農業研究センターが食味の良い「ヒノヒカリ」と多収良質の「北陸174号」を交配し育成した品種です。平成20(2008)年に誕生、平成22(2010)に品種登録されました。
「ヒノヒカリ」よりやや粒が大きく、炊き上がったごはんの粘りの強さ、味などのバランスが良い点が特徴です。また、冷めても硬くなりにくいため、お弁当やおにぎりにも向いています。
「くまさんの輝き」は、熊本県農業研究センターにおいて、「南海137号」と「中部98号」を交配して育成した品種です。平成28(2016)年に誕生し、平成30(2018)年に流通へ本格デビューしました。名前は公募から選ばれ「熊本で生まれたツヤ(輝き)の美しいお米」という意味があります。
ごはんにツヤがあり、粘りが強く食味が良いのが特徴です。また、冷めても硬くなりにくいので、お弁当やおにぎりにも向いています。28年産と29年産の「お米の食味ランキング試験」で参考品種ながら特Aを獲得しました。令和5年度産では、県北と県南の「くまさんの輝き」がA評価を獲得しています。
ほかにも、熊本県農業研究センターが開発した「わさもん」や、農研機構が育成した「あきまさり」、九州沖縄農業研究センターが育成した「にこまる」などが、熊本県内で栽培されています。
熊本県は西日本有数の米どころで、豊かな自然と水を生かし、おいしいお米が作られています。現在、品種別では「ヒノヒカリ」が最も多く作付けされていますが、「森のくまさん」や「くまさんの力」「くまさんの輝き」など、熊本県が開発したオリジナル品種の栽培も広がっています。中でも「くまさんの輝き」は、本格デビューから数年のまだ新しい品種です。ぜひ、一度味わってみてください。
(おいしいごはん研究チーム)

 お得な会員特典
お得な会員特典 新規会員登録
新規会員登録 ログイン
ログイン 検索
検索
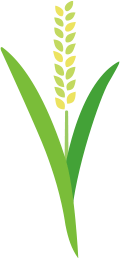















正しい保存方法でお米の美味しさをキープ! 真空パックも過信しないで!